 |
| �|���g������p�فi2001�j |
�@���₩�ȔL��ɗd�����F����Y�킹�����D�A�t�����\���[�Y�E�A���k�[����m�����̂́A1958�N����̉f��g���L�h��ʂ��Ăł����B����1962�N���̂��Ƃł��B�X������Ă���ƁA���������ɓ\��ꂽ�����̃|�X�^�[���ڂɕt���܂����B���Z���ɋւ���ꂽ�悤�ȗނ̉f��ł͂Ȃ������Ǝv���܂����A�������X�Ƌ����Č��Ă͂����Ȃ��C�����āA���������Ȃ���ؕ����A�����ǂ��ǂ������Ȃ���ꖖ�̉f��قŌ��������L��������܂��B�f��̏o��������قǗǂ������킯�ł͂���܂��A���m�N���[���f���̒��ŁA�A�[�����h�̂悤�ɂ������肵����������I�ȃ��[�L���b�v�ƁA�d�������͋C��Y�킷�p���ɉ����A�g���L�h�̃��S���A��u�A���̐S�Ƌ��U���Ă��܂��܂����B�������A���ꂪ�|���g�K���ɊW�����i�Ɍq����ȂǂƂ͎v���Ă����܂���ł������A�A���k�[����m�������Ƃɂ���āA���̌�A���̉f��ɂ��䂩�ꂽ�̂ł��B
�@
| �g |
�Â������ꂽ�����C�� |
| |
�ł��グ��ꂽ����ꂽ�͂��� |
| |
�������̂Ă����Ȃ������� |
| |
���̊C�ɋA�邾�낤 |
| |
�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�h |
�@�@ �@�@
�@�@�@�@
�@�@�@�@
�@�@�@�@
�@�����̍��ƓI�̎�A�}���A�E���h���Q�X�̂��|���g�K���̃t�@�h�g�Â��͂����h�̈�߁i��J���q��j�Ȃ̂ł����A���̉̂��S�т�ʂ��ďd�v�Ȗ������ʂ������A�A�����E�x���k�C���ēA1954�N���f��g�ߋ���������h�̂��Ƃ�b�������킯�ł��B
 |
| �I���G���e�w�i2001�j |
�@�푈����A�҂������A�����𗠐����Ȃ��E�Q���A�ٔ��ł͖��߂ƂȂ�A��čs���̑D�����߂ă��X�{���֗����s�G�[���i�_�j�G���E�W�F�����j�B����A��x���̕v�E���̌��^���������A���X�{�����ɑI�n�������������̏��J�g���[�k�i�t�����\���[�Y�E�A���k�[���j�B�^�]��ɐg�� ����p���W�F���Ɣw���̍߂�w��������x���̖��S�l�̓�l�́A���X�{���̍`�ŏo����ɗ�����B����ɁA�J�g���[�k���N�����ɂ݁A���X�ɒǂ��p���l�x���i�g���o�[�E�n���[�h�j�B���̎O�l�����Ƃ��ēW�J����h���}���A�������O�����˂����݁A�����܂C�������������A����Ă������̕Y�������ȊX�A���X�{���ŌJ��L������̂ł��B���炭�A���k�[�����o�������A�g�Y�����h�i1949�N�j����g�����~�G�[���̎q�������h�i1995�N�j�܂ł̎O�\���{�̉f��̒��ł��A���Ԃ���ۛ��ڂł͂���܂����A�����ɂ��t�����X�f��炵���Ƃ����_�ɂ����āg�w�b�h���C�g�h�ƕ��Ԍ���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�f��g���L�h����40�N��̂���N�̏t�̂��ƁA���[�}���l�A���̋u�����X���X�{����K��邱�Ƃ��o���܂����B�e�[�W����ɐڂ����[�̃R�����V�I�L�ꂩ��ł����₩�ȃ��b�V�I�L��ցB�����ă��x���_�[�e��ʂ��k�k���Ɋɂ₩�ɏ��ƁA�{���o�����ݍL��Ə̂����傫�ȉ~�`���[�^���[�ƁA���̉��̃G�h���@���h���������ɓ˂�������܂��B
�@���̓s�s�����ł��Â��X���݂�F�Z���c�������̋u�A���t�@�}�h�E���X�g���������������ēX���o���Ă��܂��B�A���t�@�}�ŁA�R��o���t�@�h�Ɏ䂩��Ē��ɓ���܂����B���ƝR��ɖ������A����ǂ��͋������������n��܂��B�|���g�K���E�M�^�[�������炵�A���B�I�[���i�Z���M�^�[�j�ƃo�C�V���i�x�[�X�j�����q���Ƃ�A�i�U���̏����B�̂悤�ȍ����ߏւɐg�������̃t�@�f�B�X�g�i�̎�j���o�ꂵ�A��������ɍ��킹�����Ǝv���ƍ��E�ɍL���A����U��i���ĉ̂��グ�܂����B
�@�O���i�_�̃A���n���u���{�a�k���Ɉʒu����A���o�C�V���n��ɍL����t�������R�̃^�u���I��z���o���܂����B���������Β��̖��O�ł����A�g�A���h�t�@�}���g�A���h�o�C�V�����A�C�X�������k�̎x�z���ɖ��t����ꂽ�̂ł��B���X�{���͂����^�钆���߂��Ă��܂����B
�@350km���ꂽ�|���g�E�J���p�j�����w�����A�T���^�E�A�|���[�j�A�w���o���������}�A���t�@�́A98�N�|���g�K�������̉��ɂȂ����I���G���e�w�ɒ�܂�܂����BS�E�J���g���o�v�̉w�ɂ́A�ׂ��S������Ɍ������Ē���`�ɘA�����čL����A�܂�ŃK���X�̓V�W�ɂ���ĕ���ꂽ�S�b�V�b�N���z�̂悤�ł��B�y���ޕ��ɂ́AA�E�V�U���v�����A�����R���N���[�g�݂̒艮�������|���g�K�����{�ق��_�Ԍ����A�X�ɂ��̉��ɁA�e�[�W���삪�I�X�Ɨ���Ă��܂����B
 |
| �|���g�E�J���p�j�����w�i2001�j |
�@�ՐÂȋ��̈����߂�|���g������p�ق́A���͂��͂ލ��������p�̋߂��Ő���ꂽ�Ƃ��낪������ł��B�S�̃t���b�g�E�o�[�ō��ꂽ�A���p�ق�\�����S�E�^�C�v�̏���i�q�����A�t���̒��ł��̗֊s�������Ȃ���V�[�E�X���[�ɕ����яオ���Ă��܂����B�����R���N���[�g�̕ǔ݂��A�Ў����̔łɂȂ��ĘA�����đ�����������������ƁA�ˑR�����̎��E���J���Ė��邢����ɏo��v�ł��B�Ⴂ�l��q���B�ɂ���āA��̑O�̔��p�i�͑����ދ�������̂ɂȂ��Ă��܂��܂����B�����̏@���G��A���i��A�Õ���Ȃǂ������X���ɂ���悤�ł��B�����۔h�̊G�͒��N�ȏ�̐l�̂��߂ɂ��邩�̂悤�ȋ�Ȃ̂ł��B��������҂����ɂƂ��āA����̑����⊴�����R�Ȃ���������̂�����A�[�g��������܂���B����Ɋϋq�ɉ������l�������Ă��܂��ʂ̑_�������肻���ł��B�����̎q���B�������ƍ�i�̑O�ɘȂ�ł��܂����B�����A�܂�œ����������������悤�ɁB
�@�O�ϓ��l�A�������f�p�ŗ}���̌������f�U�C�����т���Ă��܂������A������p�����炱�����ɂȂ炸�A�����ł����A�C�f�A�������悤�ł��B����ɂ��āA������肵���y�n�ƖL���Ȏ��R�������p�ӂ����A���z�Ƃ͌��̗͂��A�Ƃ�P����ɂȂ炸�A�����Ǝ��R�ɐU�����邱�Ƃ������Ă���܂����B����܂Ŏ�s���X�{���ł͂Ȃ��A�����܂ł����̋K�͂̓s�s�|���g�𒆐S�Ɏ肪���Ă����V�U�̐l�ԂɐG���悤�ȍD��i�ł��B
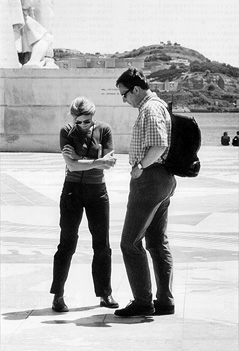 |
| �x�����̔����̍L��i2001�j |
�@���f���Ă���h�E����̓�݂ɂ́A����ό��p�̖�ڂ����ʂ����Ȃ��{���g�E���C���̉^���D���[�x�������z���┑���Ă��܂��B�ݕӂɉ������u�˒n�ɂ͑����̃��C���E�Z���[�����Ă��A���̉��ɓS�����̃h���E���C�X�ꐢ���������Ă��܂��B�|���g�E���C���̕����́A�����ʂɉ����č�����������邽�߁A�_���͓����̍��������ւ̉��ǂɗ������������Ă���̂ł��B�����̐��Y�Ƃ́A�A���J���̑����n���k���A�����̓~���z���A�ҏ��̉ĂƑΌ����A���������߂��ƂƂ̐킢�ł��B�A���R�[���x�������������������C����荂���A�Â����������Ă�B�����Ƃ��ău�����f�[�����������đ��邱�Ƃ�m��܂����B
�@����Ȕ��Â��𑠂͈�艷�x�ɕۂ���A�z���C�g�E�I�[�N���̒M�����R�Ɖ��u���ɕ��ׂ��A�ۂ��W�ɂ͎l���̐�������������A�r���e�[�W���̂Ƃ��Ă̏o�Ԃ�Â��ɑ҂��Ă��܂����B�ȑO���w�����{��̈��Ē��H����v���o���܂��B�I�̂悤�ȐF�ƊÂ��ƐG���B�i����ǂ��J��Ԃ��A���n���������̖ڏ�ɐ��Ĕ��y�����Ă��܂������A�����̖ڂ̑傫���Ɖ��x�Ǘ����̐S�ł��B�͑傫�߂���Ɣ��y�����A�����߂���ƕ��s���܂��B�n���̋Ƃ����߂����͉����ł������Ȃ̂ł��B�|���g�؍ݒ��A������������Â����C�����A�����Ă�����ȂɂȂ�A�y�j�A���j�̒��ƁA���̌���b�������܂����B

