| |
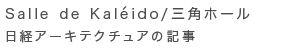

日経アーキテクチュア 2006年11月13日掲載 音響設計
常識外の三角形ホールが想定外の高音質
スケッチの束から見つけた掘り出し物
正三角形の音楽ホールがあったら──という「もしも」を、実現に向けて奔走している設計者がいる。阿佐見昭彦氏は、自ら図面を描いた三角ホールの音質を音響シュミレーションソフトで検証。その予想以上の好結果に勢いを得て、海外でも例を見ない三角ホールの実現を訴える。
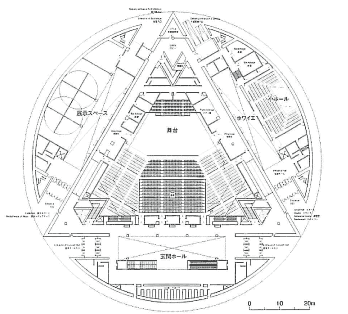 |
| 阿佐見昭彦氏が設計した三角ホール1階平面図。収容人員数は約2,200人を想定。円を包むようにして、三角形が切り取る三つのかまぼこ形の空間に、エントランスホールや楽屋、ホワイエなどを配置している。(資料:阿佐見昭彦建築・デザイン研究所) |
正方形やシューボックス(靴箱)形、アリーナ形など、世界中に様々な形状の音楽ホールがある。しかし、「約230年の歴史上、なぜか正三角形のホールは存在しなかった」と、阿佐見昭彦建築・デザイン研究所(さいたま市)の阿佐見昭彦代表は言う。「実証するまでもなく音響障害を起こす形状だと思われていた。設計者がプランをまとめづらい形でもあった」と、阻害要因を推測する。
しかし、阿佐見氏は現在、正三角形のホール(以下、三角ホール)について全く異なる見解を持っている。音響障害はほとんどなく、予想以上の高音質。感じ方は人によって異なるが、座席位置による音質のバラツキが小さい──。音響専門家の分析と、緻密なシュミレーションができる可聴システムでの検証結果を得て、こう確信した。
あるときふとふらめいた
きっかけは、フランスにある美術館の館長の一言だった。
阿佐見氏は、設計者としてだけでなく、趣味で始めた写真と彫刻でも高い評価を得ている。2005年の夏にも、仏・トルコアン市の美術館で個展を開いた。その企画時に、館長から「建築家なのだから建築も展示してほしい」と言われたのだ。
「実際に設計した建築を展示しても面白くない。何か新しいものを・・・と思いあぐねていたとき、たまたま自宅で、あるコンペ時に描いたスケッチの束を見つけた」と阿佐見氏は振り返る。
石本建築事務所に在籍していたときは、田園ホール・エローラ(埼玉県松伏町、1988年竣工)や所沢市民文化センター(埼玉県所沢市、1993年竣工)など、ホールの設計に多くかかわってきた。見つけ出したスケッチも、12〜13年前に国内のある自治体が催したホールのコンペのために描いたものだ。それが三角ホールの原型になった。
一般的に、客席に向かってすぼまる逆扇形の音楽ホールは音が良いと言われる。あるとき正三角形を描いていて、ふと「この中にステージを設けると、音響に良い逆扇形が三つできる」とひらめいた。
スケッチを見つけてから、阿佐見氏は約2200人を収容する三角ホールの図面を描き上げる。期間は約1カ月。面白いものになりそうだ、という予感はあった。しかし、三角ホールが、音楽ホールの専門家に半ばタブー視されていることは間違いない。音響専門家のお墨付きのようなものが欲しい。そこで相談を持ちかけたのが、東京大学名誉教授の安岡正人氏だった。
| ●ホール形状別の音線密度のシュミレーション結果 |
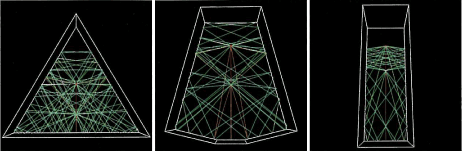 |
| 正三角形の音楽ホールは、同規模の扇形やシューボックス形に比べて、「音がある壁にぶつかって反射し、次の壁にぶつかるまでの平均的な距離(平均時間行路)が短い」(安岡氏)。また、ある一点において、均質にあらゆる方向から反射音が届き、音線密度が高い(資料:五洋建設) |
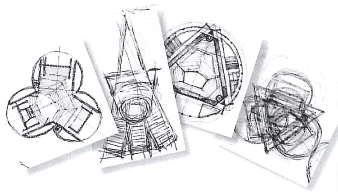 |
| 阿佐見氏が石本建築事務所在籍時に描いていたスケッチ。ある公共ホールのコンペのために描いたものだった |
 |
阿佐見昭彦建築・デザイン研究所代表
阿佐見 昭彦氏 |
|
東京理科大学建築学科教授
安岡 正人氏 |
|
万華鏡のような反響の妙
現在、東京理科大学建築学科で建築環境工学を専攻する安岡氏は、可児市文化創造センターala(岐阜県可児市、2002年竣工)など、数多くのホールの音響設計にかかわってきた。「そんな大家の意見を仰ぎたかった」(阿佐見氏)。
図面を見た安岡氏は、「万華鏡を思い浮かべた」と言う。「正三角形の筒に入れられたビーズなどの色が、三方を包む鏡に反対して密度の高い音場ができるのでは、と思った。」
安岡氏は、受け取った図面と模型を五洋建設に持ち込んだ。同社には、安岡氏がソフトの改訂にかかわった音響の可聴シュミレーションシステムがあったからだ。当初「コンサートホール」と呼ばれていたそのソフトは、ホールの図面データを入力し、音源を設定すると、指定した座席で聴こえる音を再生する(下部“記者も聞いた三角ホールの音質”を参照)。
「全席S席も夢ではない」
図面を渡してから3カ月後、阿佐見氏は安岡氏から「音を聞きに来てほしい」という電話を受け取る。五洋建設本社ビルの一室で、可聴システムによるデモンストレーションを聴いた阿佐見氏は驚いた。音響障害が一つもなかったからだ。
余韻のある響きを持ちながら、楽器の各パートが分離して、どの方向から聴こえるかがわかる。何より驚いたのは、座席による音質のバラツキが少ないことだ。
「極端に言えば、全席がS席のホールも夢ではないのではないか。」阿佐見氏は興奮を隠しきれなかった。
なぜ音質が良かったのか。最も大きな理由は、同規模のホールと同程度の収容人員数を確保しながら、舞台正面の壁を前に出させたことだと、二人は分析している。
座席空間の奥行きが短くなるから、音源から客席への距離が総じて近くなり、音の強さに影響がある直接音がどの席へも早く届く。広がりを感じさせる反射音も、左右の側壁から素早く客席に返ってくる。
一般に、チケットの値段が高い1階前側の席は、横からの反射音が少なく、音の広がりに欠けるきらいがあるという。しかし、三角ホールのシュミレーションでは、「場内のどこでも、音の響きが豊かで、極端に悪条件の席がなかった」(安岡氏)。
さらに興味深い結果も出た。2秒程度が標準的な残響時間を3.5秒。ちょうど教会のような環境に設定しても、音がクリアに聴こえる。楽器演奏に限らない。例えば、響き過ぎると聴き取れなくなるスピーチのような人の語りでも問題がないようなのだ。
「アナウンサーのようにはっきりしゃべる人ならよいが、自治体の首長など普通の人の語りが聴き取れないという苦情は、ホールのオープン後に多い」(阿佐見氏)。
楽器演奏に合わせた響きを重んじる音響設計が、スピーチのようにはっきり聴こえるべき音ではあだになることがある。この問題が、三角ホールでは生じにくいという。「早く届く反射音が直接音を補い、遅れた残響音が邪魔にならないからだ」(安岡氏)。
建築学会で論文を発表予定
もちろん課題もある。例えば、音楽ホールに共通するカレーレーションと呼ばれる現象だ。客席の中心線に位置する座席で特殊な音が聴こえるのだが、これは解決できていない。
設計上の課題もある。形が形だけにコンパクトに設計できない。鋭角に過ぎる三つの隅をどのように処理するか、設計上の工夫が必要だ。
シュミレーションの音は精度をいくら高めても実物とは異なる。「何より、実物をつくりたい」。これが、阿佐見氏、安岡氏に共通する思いだ。
来年、日本建築学会で三角ホールの音響特性に関する論文の発表を予定している。そのほか国内外を問わず、発注者探しのため、阿佐見氏はピーアールに励む。 (高市 清治)
1. 記者も聴いた三角ホールの音質
阿佐見氏と安岡氏は、パソコンなどを利用した音響の可聴シュミレーションシステムの価値を高く評価している。
「従来も、10分の1の模型をつくり、10倍の周波数を使って、音の聴こえ方を評することはあった」(安岡氏)。しかし、模型を作成できるのは設計の最終段階だ。音の聴こえ方に問題があり、いざ設計変更となったときのコストは高くつく。そもそも模型をつくる自体、「規模にもよるが数百万円はかかる」(安岡氏)など、高コストだった。
図面データを入力してホールの音響を確認できる可聴シュミレーションシステムを使えば、基本設計の段階でも、ある程度の精度で音の聴こえ方を確認できる。この段階なら設計変更も難しくない。
三角ホールのシュミレーションに使用した可聴システムは、五洋建設が開発したもの。音がどの壁に当たって、どのように反射するかという音線の反射回数を30回まで計算する。「1回、1回の反射音の減衰量まで加味しており、かなり優れたソフトだ」と安岡氏も太鼓判を押す。
「ホール設計時はもちろん、オープン後の音響トラブルに対応する際にも利用されている」。五洋建設建築本部建築エンジニアリング部の末永義明部長は、ソフトの用途について、こう説明する。
 |
|
|
五洋建設が開発した音響の可聴シュミレーションソフトの図面。座席位置を変えてスピーチも聴いてみたが、反射し過ぎて聴き取れないことはなかった |
|
|
|
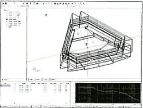 |
|
|
ボーズ社がスピーカーの音響確認用に開発したモデラーでも視聴。サウンドシステムは、音の裸の状態で聴ける、ボース社のオーディショナーを利用した |
|
|
今回、記者も実際に試聴してみた。カルテットの演奏やスピーチを1階前部、後部、2階後部角など、座席の位置を変えて試聴したが、それほど大きな違いを感じなかった。広がりのある音響だが、各楽器の分離もよい。
阿佐見氏らが、結果の確度を高めるためにシュミレーションを依頼したボーズ社のシステムでも試聴した。結果はほぼ同じ。こうした可聴システムで聴く限りでは、三角ホールの音質は広がりのある良い音に聴こえた。
|
|

