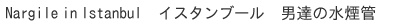


NII-001
|

NII-002
|

NII-003
|

NII-004
|

NII-005
|

NII-006
|

NII-007
|

NII-008
|

NII-009
|

NII-010
|

NII-011
|

NII-012
|

NII-013
|

NII-014
|

NII-015
|

NII-016
|

NII-017
|

NII-018
|

NII-019
|

NII-020
|
[Nargile in Istanbul “イスタンブール 男達の水煙管”]1990年夏、突如始まったイラク湾岸紛争は底なしの長期戦争になると予想されていたが、翌91年早春、最後はあまりにもあっけなく終局を迎えた。しかし渡航自粛勧告は続き、不穏な情勢の中で航空機はガラ空きだった。明け方四時、クルド族の住む山岳高地を越え、ノアの箱舟の伝説で知られるアララト山を北に望みながらヴァン湖の上空を飛び、南回りのSQは成田出発後20時間をかけて無事早朝のアタチュルク空港に着陸した。
イスタンブールの中心は主に三つの区域から成り立っている。ボスフォラス海峡を挟んだ東(東洋)と西(西洋)。そして更にその西側部分が、金角湾を挟んだ南(旧市街)と北(新市街)だ。この新旧二つの区域を結ぶ大動脈が彼の有名なガラタ橋なのだが、驚くべきことに、この橋はその上を夥しい車がひっきりなしに走る木造の巨大な浮橋なのだ。
嘗てトルコ軍が、東ローマ帝国の首都であったこの都市、コンスタンチノープルを攻撃した時、金角湾に木造の船を浮かばせ、鎖で縛り付けながら連結して進入路となし、難攻不落といわれたこの都市を陥落せしめたことはつとに有名な話である。
ユニークなのはその橋の下、海面と道路面との隙間を利用してショッピングアーケードが設けられていることだ。私の目指す場所、ナルギレ・カフェ《ERZURUM》はこの中にあった。チャイを飲み、トルコ語で水煙管を意味するNargileが吸える茶店である。
長年、分厚いペンキを塗りたくった木造の船室風の粗末な室内でも、壁に掛けられたケマル・アタチュルクの肖像画は圧倒的な存在感があった。60年前に祖父がこの店の権利を買い取り、以来ここで営業を続けているのだと語る老店主が無言で暗い店の奥を指差す先に、まるでゴッホの絵から抜け出て来たばかりのような男が一見恍惚した面持ちでパイプを銜えていた。部屋は“巣窟風”の雰囲気で、禁断の場所にうっかり足を踏み入れてしまったような怪しい雰囲気が立ち込めていた。くびれた透明なガラス壜。ステンレスの灰受皿。湿った葉タバコを巻きつける紡錘形の陶器芯。握りにキリム織布を貼り付けた煙管。種火用の豆炭と銅製トルコ式サモワール。これがナルギレとの初めての出会いだった。
翌1992年6月。昨年撮影したこの二人の男達の記憶が生々しい中、私はアンカラのスタッドホテルのロビーで、ガイドのデイルメンジと打ち合わせをしていた。二、三ヶ月前のこと、あの木造のガラタ橋が火災を起こし、海の藻屑と消え去った事を偶然耳にして絶句した。直ぐ隣には鉄筋コンクリート造の新ガラタ橋が竣工を二ヵ月後に控え、ほぼ完成していたという。当然《ERZURUM》も60年の歴史を背負いながら、煙が水中を通り抜ける際に発生する、あの水煙管の独特なゴボ、ゴボ、ゴボという音と共に喪失してしまった。当然、あの老店主も、ゴッホ男も、その後杳として行方は知れない。写真の持つ記録性《その場に居合わせること》の深遠さ、一期一会で邂逅する偶然性・神秘性を再認識し、一見何の変哲も無さそうな日常の出来事にも多くのドラマのあることを知らされる。
|

