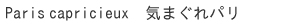


PCA-001
|

PCA-002
|

PCA-003
|

PCA-004
|

PCA-005
|

PCA-006
|

PCA-007
|

PCA-008
|

PCA-009
|

PCA-010
|

PCA-011
|

PCA-012
|

PCA-013
|

PCA-014
|

PCA-015
|

PCA-016
|

PCA-017
|

PCA-018
|

PCA-019
|

PCA-020
|
[Paris capricieux “気まぐれパリ”]2002年秋のこと、何故か僕はパリにいる。七区、サン・ドミニク通りに面する小さなホテル。一階は古いブラッスリー。バー・カウンター脇の受付が鍵を受け渡すフロント。毎日、客席を通り抜け、木造の階段を上って右に曲がり、突き当たりの扉を開き、細い階段を更に上るとやっとホテルの三階。エレベーターなどは無い。とにかく毎日がこんな具合だからレストランで働く全ての従業員に顔を覚えられてしまう。言葉もよく喋れないのに、僕が通ると皆こちらを向き、笑顔を振り撒いて挨拶をする。初日は大いに驚いたし、照れもした。でも翌日から、僕も笑顔を返して手を横に振るのだ。まるで一躍、店のオーナーにでもなったよう。それがパリ。
毎日ホテルに出入りして奇妙な光景に出会う。ロンシャン競馬場で凱旋門賞の撮影を済ませて帰ってきた時のこと。やはり今日もいる。入り口の左側が彼の専用席になっている。ワインを飲み、肉を食べているのは七十過ぎの老人。足元には茶と白の斑の、どでかい犬が蹲っている。僕が店に入ると老人は必ずこちらに向き直ってウィンクをする。鍵を受け取りに受付へ行くと、正面の壁に一枚の顔写真が貼られている。ちょうど、レストランの社長がいたので、僕は自信をもってこう断言する。入り口の例のムッシューだけど、あなたの父さんなんですね。社長は顔を横に振りながら答える。ノン、ああして毎日来ているから敬意を表して飾っているのさ。それがパリ。
アレクサンドル三世橋に向かって東西に広がるアンヴァリッド前の公園。一直線に、幾何学的に植えられたマロニエの葉が黄一色に染まっている。この一週間、珍しく雨が降らずに、乾燥した空気もどことなく暖かい。アルマ橋を望みながら、昼にカフェで食べるサラダが彩り鮮やかな配色でじつに美味い。ドレッシングに混ぜられたレモンと胡椒の芳しい澄んだ香りが緩やかに立ち上る。一面に紅葉した景色を見遣りながら、外で飲む白ワインとチーズがこれまた美味い。でも、通りを行き交うパリジャン達は前方だけを凝視し、皆いちおうに足が速い。こんな良い天気でも驟然として雨が振り出すことが、予めわかっているかのような歩み。それがパリ。
モンマルトルの丘に登る。お奨めの上りのコースは二つ。アベス広場からダリ博物館経由でテルトル広場へ。運がよければ蚤の市で、思わぬ掘り出し物にでも出会うかもしれないから。もう一つはラマルク・コーランクールから急峻な階段を上ってサン・ピエール教会へ。細い階段ですれ違う《行きずり》に胸がときめく。夕方、サクレ・クールを背に佇むと、夥しい建物の西側の壁がジグソーパズルのように夕陽を浴び、オレンジ色に染まりながら裏側の黒い影と混ざり合う。パリのもう一方の丘に建つパンテオンを遥かに望む古典的風景。その手前には赤と青のポンピドゥーの前衛的風景。絵になり過ぎるからなかなかシャッターを押せない。それがパリ。
バスチーユで若い黒人女と行きずり会う。黒いマントを纏い、褐色の肌が健康的で美しい。フードから覗く黄と茶のマフラーがとても新鮮。前に下げているひら織りの四角いポシェットがアクセントになって印象的。一瞬ハッとするが、十メートル、二十メートルと離れて通り過ぎて行く。しかし僕は予想を裏切って突然振り返える。まっしぐらに彼女に近づいて、写真を撮らせて欲しいと頼み込む。すると女は名刺を見せて欲しいと望むから、僕は躊躇無くそれを手渡す。彼女は名刺と顔を見比べながら、一瞬間をおいて、ウィ、私はセリーヌよと言う。後日写真を一枚送ってねとも付け加える。僕は《もちろん》と、ひとこと言って一本を撮り終える。それがパリ。
晩秋、冷たい雨の降りしきる中、吐く息は白い。もう冬はそこ。セーヌ川に面する古本屋も既にたたまれた店が多い。僕はサンミッシェルからサンタンドレ・デザール通りを歩いている。何処からか温かく甘い匂いが仄かに漂よって鼻腔を刺激する。鋼鉄の円盤の上で、小さい熊手を巧みに操る腕の良い庭師はクレープ屋。鮮やかなナイフ捌きでたたみ込まれる、薄くて白いパンケーキ。お決まりの注文は搾り出したレモン汁と砂糖だけのシンプルなクレープ。この季節に街を彷徨うと、これが病みつきになる。僕はクレープ屋が抜け目なく放つ甘い誘惑から決して逃れられない。クレープを包む薄い紙を通して伝わる、温かさ、柔らかさ、そして心地よい香り。それがパリ。
オデオンからセーヌ川へ向かいながらラビリンスをあてどなく彷徨う。中心はセーヌ通り。ショウ・ウィンドーを通して見つけたアルマンのブロンズ。それにピエトロ・サンタのミトライとはヴェニス以来だが突然の出会い。でもニースの彫刻家マダム・レミーこそ予期しない一番の偶然だ。胸が騒ぐ芸術との邂逅。脇道に面する細い鉄枠の古風なショップ・ウィンドーは画材屋。そこで売られているキャンソンのスケッチブックとオーストリアの鉛筆を使うと、不思議なほど巧く絵が描けてしまう。僕は角のパレットに来ると必ずエスプレッソを飲む。アフリカ、アジア、ミクロネシアのアンチークと芸術作品とが奇妙なハーモニーを奏でる。それがパリ。
バスチーユがオペラ、ガルニエはバレーと決まったのに、結局、両方を気にして曖昧な決着。オペラにはオペラとしての形式があり、建築に対してもその時代の様式を要求する。観客もまたその時代の様式空間に酔いしれる。現代建築家にとってこの形式や様式との戦いは辛い。12月31日、恒例の年末イヴェント。ガルニエ・オペラでバランシンの“ジュエルズ”を観る。アリーナ席でもボックス席でもなく、念願の天井桟敷の最前部。わずか10ユーロのくせにこれが意外に良く見え舞台の三分の二。パレ・ロワイヤルからオペラ座までは、いわゆるおのぼりさん通り。黒マントに黒帽子、赤いマフラーを巻きつけて歩けば、男はみんなアリスティド・ブリュアンだ。
|

