 |
| �����O�V���g���[�Z�E�M�������[�i1996�j |
�@�P���g��̃E�B���h�{�i�i�E�B���̒��j���ꌹ�Ƃ���E�B�[���́A1910�N�ɐl��200�����z���A�����̃��[���b�p�ł̓����h���A�p���A�x�������ƕ��ԑ�s��ł����B20���I���I���ɋ߂Â����A���߂ăE�B�[���̊X�ɋ����������܂����B19���I���A���z�E�Ƌ�E�H�|�E�O���t�B�b�N�E�G��E���y�Ȃǂ̌|�p����ŁA���I�ȃG�|�b�N�E���[�L���O���I�ɐ����������s�s�E�B�[����I�сA����20���I�������߂悤�Ǝv���܂����B700�N�������h���̃I�[�X�g���[�鍑���x���������n�v�X�u���O�Ƃ̈�Y��19�`20���I�����ɂ����Ĉ�C�ɊX�ɗ���o���A���{�Ƃ▯�O�̃G�l���M�[�Ƌ��Ɉ�ĂɊJ�Ԃ����̂͂����m�̒ʂ�ł��B���[���b�p�ł̓u���{���ƁA���}�m�t�ƂȂǂ��s��ȉ�����z�������h���܂������A����ł�200�`300�N�ł��B700�N�������������̓n�u�X�u���O�Ƃ�����������܂���B
�@��ʐ��Y�Ƃ����`�����Y�Ɗv���ɑ��锽�����㉟�����A19���I�����̃C�M���X�ł́A�E�B���A���E�����X���A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�^�����N�����܂����B����E�B�[���ł�19���I�O���A���z�ɑ�����ς┽������A�����Ɠ���I�Ȃ��̂ɖڂ������悤�Ƃ����������̒��ŁA���s���I�Ȑ������ɑ������r�[�_�[�}�C���[�l�������s���Ă��܂����B�������|�p���������܂ސV�����g�́A�����Ɖؗ�ɁA�����Ă����Ɖߌ��ɁA���̓�������C�ɉ��������A1919�N�A�n�u�X�u���O�鍑�͏I�����}�����̂ł��B
�@���z�Ƃł́A�I�b�g�[�E���O�i�[�i1841�|1918�j�A���O�i�[�̒�q�ŃE�B�[���H�[��ݗ��������[�[�t�E�z�t�}���i1870�|1956�j�A�z�t�}���Ƃ͓��N�E�����̐��܂�ŁA���U���C�o���Ƃ��Ĕᔻ�𑱂����A�h�t���E���[�X�i1870�|1933�j�A�����ă��[�t�E�I���u���b�q�i1867�|1908�j�Ȃǂ����X�g�A�b�v����܂��B�����h�̓W���{�݂ł���A�|�p�^���̋L�O�I�{�݂ł�����Z�Z�b�V�����i�����h�j�ق܂Ō��ĂĂ��܂����̎���A�Љ�́A�|�p�ɑ���G�l���M�[�ɂ͐��܂������̂�����܂��B�ِ��ʂɃ��f���[�T�̊炪�O���ԃ����[�t���A���{�l���猩��Ήߌ��ȃf�U�C���ł����A�s����ɂ͂��̌|�p���A�|�p�ɂ͂��̎��R���t�̃X���[�K������A�����B����������[�h���Ă���Ƃ̎�X�����������v���v�������Ă��܂��B1897�N�ɂ́A�N�����g�A���[�O�i�[�A�z�t�}���A���U�[���ɂ���ăE�B�[�������h���ݗ�����A20���I�����A�����I�Ȍ|�p�^���Ƃ��ăE�B�[���H�[�ݏo�����̂ł����B
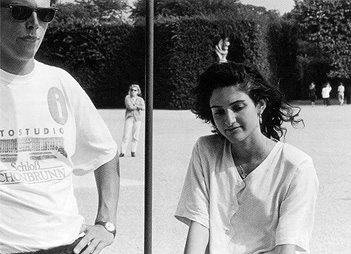 |
| �V�F�[���u�����̒�Łi1991�j |
�@��Ƃɂ��Ă̓N�����g�A�V�[���A�R�R�V���J�Ȃǂ��������܂��B���Ď����Ђ��������Ζ{���z�������̑n�ݎҁA�Ζ{��v���i1894�|1963�j���n�������܂ɁA�N�����g�̓��M�Ȃ�X�P�b�`�W����肵�A���̎��\�N��A���q���̋v�j�����q�������Ă������������Ƃ��v���o���܂��B���̗��Ńo�E�n�E�X�����߂ĖK�ꂽ���{�l���z�Ƃ��Ζ{��v���ł���A���p�]�_�Ƃ̒��c��V���ł����B1922�N�A�Ζ{�͕��e���c�����s���Y���������A�C�܂܂Ȉ�l���Ƃ��ēn�������悤�ł��B������w�𑲋Ƃ��A�|���H���X�ɓ��Ђ�����̂��Ƃ�28�ł����B�匚�z�ƁA�����|�p�Ƃł��낤�Ƃ��K�˂đ�����������A���ł����āA�ʐ^���B��܂���A���Ђ���������ł�낤�ƈӋC�����ł��������Ƃ��A���z���i1924�j����ǂݎ��܂��B�x�������A�|�c�_���X�̔��p���X�ŊJ����Ă����A����M�l�|�p�Ƃ̓W����ŋ��R������̂��A���C�}�[�����痈�Ă����J���f�B���X�L�[�v�Ȃł��B���̎��A�ނ̓o�E�n�E�X�����̐E�ɂ���A����Ƃ������ɗ������悤�Ɋ��߂܂����B�������ĐΖ{�̓J���f�B���X�L�[�ɏЉ��āA�x�������ŃO���s�E�X�ɉ�����̂ł����B
�@1954�N5��19���A�O���s�E�X�����������܁A�Ζ{��60�ŁA�v�Ȃ̔��܂����z�e���܂œ͂����ʕ��ɓY�����Ζ{�̎莆���c���Ă��܂��B�莆�ɂ́A�����x�������ŐΖ{���O���s�E�X�ɉ�����A����30�N�O�̑N��Ȉ�ۂ��A�V�J�S�E�g���r���[���̐v���Z�ɂ��Ă̂��ƂȂǂ��܂߁Aprogressive�Ƃ����P�ꂪ�J��Ԃ���ďڍׂɒԂ��Ă��܂��B���[�[�t�E�z�t�}���ƃE�B�[���H�[���u�����b�Z���̃X�g�b�N���[�@�ŁA���z�A�����A�Ƌ�A�H��A�뉀�܂Ńf�U�C�������悤�ɁA�Ζ{���������ݗ��Ԃ��Ȃ����ƁA�Z��z�₻�̃C���e���A�����łȂ��A�Ƌ��H��ނ̐v�܂ł��Ă���̂ł��B�ۑ�����Ă���}�ʂ͊C�V����Y�̍�}������A�ނɐH��ނ̃f�U�C����S�����������Ƃ��ǂ�������܂��B
 |
| �n�[�X�n�E�X�i1996�j |
�@�N�����g�͕������Ŏt�ł��������Ƃ�A�����ٕt���H�|�w�Z�ɓ��w�������ƂŁA���Ƀf�U�C�������ƂƂ��Ă̖����Ă��܂����B��i�̗����ɂ͂��̐���������m�邱�Ƃ��d�v�ł��B�N�����g�̊G�ɂ͊Ô��ŗd���ȃG���X�����łȂ��A��Ɏ����t���܂Ƃ��Ă���ƌ����܂����A�����𑽗p�������ƂȂǂ����������悤�ɁA�H�|�I���O���t�B�J���ȏ����𑽗p�����f�U�C�����ɂ����̓��������o�����̂ł��B�܂��A���t�@�G���O�h�Ɍ�����t�@���E�t�@�^���I�ȏ�������A���̋��Ӑ��̈����ɂ��傫�������������܂��B
�@�����쎟�n�I�Șb���ɂȂ�܂����A2006�N�A�N�����g��w�A�f�[���E�u���b�z�o�E�A�[�̏ё�I�x�̊G���j��ō��l��1��3500���h���i160���~�j�Ŕ��p���ꂽ�j���[�X�ɂ͋������ւ����܂���B1990�N�A�S�b�z�̖���u��t�K�V�F�̏ё��v�̎��͓��{�l�̎��ƉƂł������A8250���h���i125���~�j�ŋV�������̂ł��B������2004�N�A�s�J�\�̑�\��u�p�C�v�������N�v��1��416���h���i114���~�j�ŗ��D����܂����B�������ł��B2006�N�㔼�A�W���N�\���E�{���b�N��No.5,1948�Ɩ��t����ꂽ�h���b�s���O�̎�@�ŕ`���ꂽ�c2.5m�̍�i��1��4�疜�h���i165���~�j�ŗ��D���ꂽ�L����ڂɂ��܂������A��̂ǂ̂悤�Ȍv�Z�ł��̂悤�Ȍ��ʂɂȂ�̂��A�|�p�����̐��E�͓��ꗝ���ł��܂���B
 |
| �����O�̊X�p�Łi1996�j |
�@���āA���y�Ɉڂ�܂��傤�B�ނ̗L���ȃE�B�[���y�F����̃O���[�T�[�U�[���ŃE�B�[���t�B���������Ƃ́A�c�O�Ȃ��玄�͂܂�����܂���B�u���[���X�U�[���i���z�[���j�Ŏ����y������A�{���w�����x���̌����Ă͂���̂ł����B�������E�B�[���t�B���́A�V���^�[�c�E�I�p�[�i�I�y�����j�œ���Ă��܂��B����1991�N�A�|�[�����h�̍�ȉƃy���f���b�L�́s�������ʁt�ŁA����1996�N�AR.�V���g���E�X�̉̌��̂����A�ł��㉉������Ƃ����s�i�N�\�X���̃A���A�h�l�t�ł��B
�@1996�N�t�A�v���n�̋A�H�E�B�[���ɗ���������Ƃ��̂��Ƃł��B�z�e����ʂ��ē��肵���`�P�b�g��PARTERRE-8�̍őO��i�{�b�N�X�V�[�g��1�K���葤�����j�ł����B��{�̑�b������葤�ߐ��ʂɌ����Ă��܂��B�^���Ԃȃr���[�h�œ������ꂽ���̐Ȃł���ʂ̃J�e�S���[�Ȃ̂ł����A�܂�ŋM���̒��ԓ���������悤�ȍ��o�Ɋׂ�܂�����s�v�c�ł��B����܂ł́A1�K���y�Ԃ�PARKETT��PARTERRE����ł�������K�^�ł����B��z�𗊂R���V�F���W�F����́A�����ؕ��̏�ɍX��40%�̃`���[�W������邪�ǂ����邩�Ɛu�˂��܂����B�������A���́s�i�N�\�X���̃A���A�h�l�t���Ȃƒ������Ō�̃I�y���ɂȂ�܂����B�S�Ă̊ϏO�ɂƂ��ċL���Ɏc��悤�ȃI�y���ł�������A���R�̃X�^���f�B���O�E�I�x�[�V�����B����������Đɂ��݂Ȃ������ہA���̃o���R�j�[�ȂɘA�Ȃ�ϏO���m�̖���̘A�ъ��Ƃ����܂����A���邱�̐Ȃɍ��ꂽ��тƌւ�ɐZ�肫�霒�����ɂ͏��X�C�p�����������̂�����܂����B
�@

